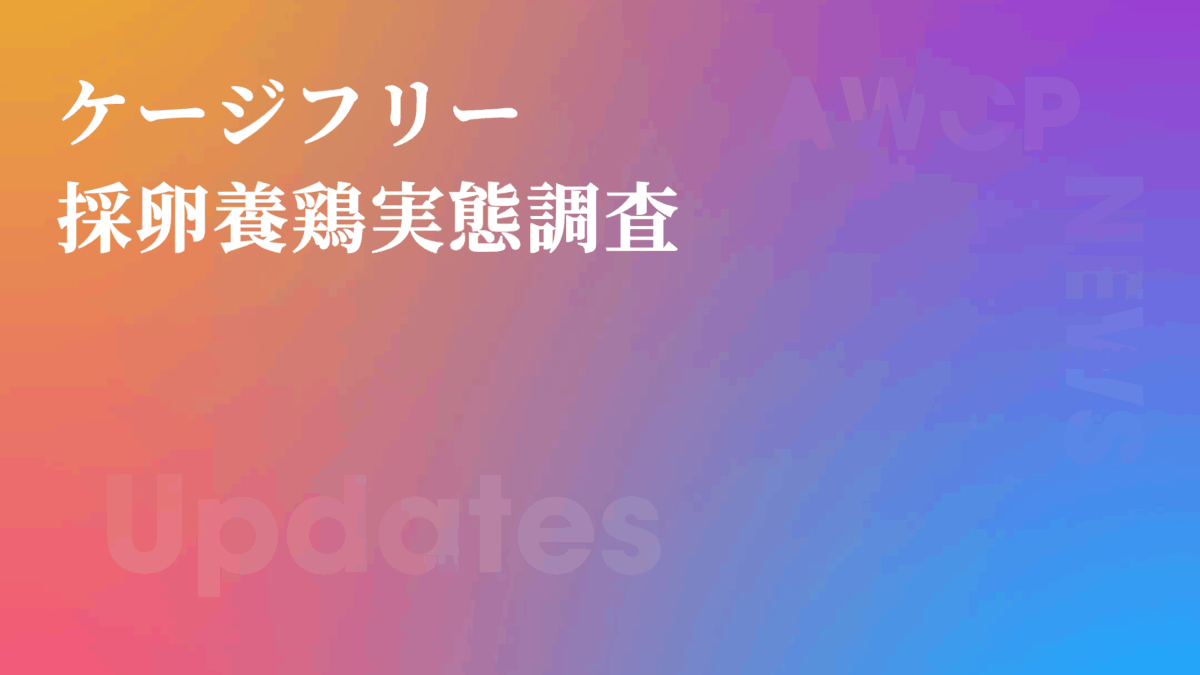本記事では、麻布大学の大木茂教授が発表した調査から見えてきた現状と未来を整理します。
麻布大学・動物資源経済学研究室の大木茂教授が、「ケージフリー採卵養鶏 実態調査」報告を発表いたしました。研究のリンク:https://lab-navi.azabu-u.ac.jp/va-10/6e86149cd9a1254e8b15fa0f5ab5e82d_1.pdf
1. 導入:なぜ今、ケージフリー養鶏の実態調査が重要なのか?
あなたが毎日食べている卵は、どんな環境で産まれているかご存知ですか?世界的にアニマルウェルフェア(動物福祉)への関心が高まり、ケージフリー養鶏が主流になりつつあります。しかし、日本ではこれまでケージフリー養鶏に関する詳細なデータが不足していたことが課題として挙げられていました。その理由は、養鶏業界における実態が正確に把握できないからです。
その中で、麻布大学・動物資源経済学研究室が画期的な実態調査を実施し、その報告書が発表されました。アニマルウェルフェア・コーポレート・パートナーズとしてこのような重要な調査結果が発表されたことを歓迎するとともに、是非多くの方々にも周知いただきたいと思い、簡単な解説記事をここに公開いたします。
2. 調査概要:何が、どのように調べられたのか?
- 調査主体: 麻布大学 動物資源経済学研究室
- 調査期間: 2025年2月~3月(短期間でこれだけの回答を得たことの意義)
- 調査対象: 全国の採卵養鶏経営691戸(有効回答138戸)
- 調査内容: ケージフリー養鶏の実態(飼養羽数、飼養方法、飼養スペース、課題、開始理由、拡大意欲など)
3. 調査結果のハイライト:ここがポイント!
速報版の主要な発見を分かりやすく解説いたします
- ケージフリー飼養羽数の現状:
- 「ケージフリー飼養羽数の比率は約3.17%」
- この数字が何を意味するのでしょうか。まだ養鶏業界においては未だ少数派でありますが、しかし着実にその存在感を増しています。
米国のOpen Philanthropy(6月20日発信)のニュースレターによれば、一進一退はあるものの、現在、米国採卵鶏の45% 、欧州採卵鶏の62% 、英国採卵鶏の82%がケージフリー飼育になっているということです。これは、10年前と比較してそれぞれ約13%、44%、50%増加しています。日本では3.17%でありますが、現在変わりたい企業も増えているので、今後ケージフリー羽数も上昇してくると期待しています。
参考記事:https://farmanimalwelfare.substack.com/p/crunch-time-for-cage-free
- ケージフリー拡大への意欲:
- また、「ケージフリー拡大に前向きな経営は74%」という数字はとてもポジティブに捉えて良いと考えます。日本の養鶏業界にもケージフリー化への意欲があることを示す重要な兆候であります。
- ケージフリーを始めた理由:
- 「付加価値販売のため」が共通して高いが、CF経営と並行経営で理由が異なる点がこの調査から明らかになった特徴と言えるでしょう。
- 特に「鶏の健康増進」「鶏の福祉」「卵の栄養・おいしさ向上」といったアニマルウェルフェア視点がCF経営で強い。
- 技術的・経営的課題:
- 「つつきやいじめ」「巣外卵」「汚卵」などの技術的課題があることがわかります。
- また、「販売価格」「販売先の開拓」「労働時間の増加」などの経営的課題も示されており、いかにしてこれらの課題を解決する道筋を示していくか、それがケージフリー化推進における具体的な障壁であると言えます。AWCPは、これらの課題解決に前向きに取り組んでいきたいと考えています。
- 特に「日本のケージフリー生産基準が公的に定められていないこと」という課題については、早急に取り組むべき点でしょう。
4. 考察と提言:この調査結果から何が見えるか?
- 現状認識: 日本のケージフリー養鶏はまだ黎明期だが、着実に進展しており、生産者の意欲も高いこと。
- 課題の明確化: 技術的・経営的課題が明確になったことで、今後の支援策や研究開発の方向性が見えてきたこと。
- NPOの役割:
- 消費者への啓発(ケージフリー卵の選択の重要性)。
- 生産者への情報提供・技術支援。
- 政策提言(ケージフリー生産基準の策定など)。
- サプライチェーン全体での協力の必要性。
課題はあるものの、この調査結果は日本のケージフリー化推進に大きな一歩となっているでしょう。
5. 私たちにできること
是非このブログ記事や調査結果をSNSなどでシェアしていただけますと幸いです。養鶏業界は鳥インフルエンザに悩まされており、事業継続が危ぶまれる養鶏家も多く生まれてしまっています。調査結果にもあったように、ケージフリーで育てられた鶏卵は付加価値がついているために少々価格が高く思われます。しかし、日々の買い物で数回に1回でもケージフリー卵を選ぶことで、ケージフリーに取り組む養鶏家へのご支援をいただけるとありがたいです。